|
|
| 序 |
そもそも人間の発声器官は歌声を発する機構になっていて、その仕組みを動かす為に多くの筋肉が備わっています。それら筋肉のひとつひとつが活力に満ちた状態であれば、誰の発声器官も自ずと本来の歌声の能力を発揮するはずです。
ここではフレデリック・フースラーの発声研究をご紹介したいと思うのですが、フースラーの研究は西洋の声楽を対象にしていますので、骨格も文化も異なる吟詠の発声にすべてそのまま持ってくることはできないでしょう。しかしその内容には人類共通の発声器官の真理が多く含まれていると確信し、そういう部分を吸い上げてここにご紹介したいと思います。
目的はあくまで発声器官のリハビリであって、吟じ方(歌い方)はまた別の才能であると考えてください。 |
初期のアナログ・シンセサイザーは欲しい音色や音質を自分で作り出さねばなりませんでした。その作業に必要なことは音の原理や様々な楽器のしくみなど、音に関する知識をできるだけ多く得ることでした。
音に対する興味は最終的には人間の歌声に向かいます。ところが、人間の歌声は自分のもっとも近くにありながら、音や楽器のことよりも分からないことだらけでした。
発声に関係する書物や情報を探してみたのですが、残念ながら目にしたものの中には私の疑問を完全に解決してくれるものはありませんでした。
そんな時、偶然にフレデリック・フースラーという発声研究家の著書に出会ったのです。
その内容は、発声に関する一般的な認識とは大きく異なるものでした。そのような突飛な著書を信頼できた第一の理由は、人間の声帯がどのようなしくみで旋律を奏でるのか、という疑問に対する答えでした。
過去には、「管楽器のように喉の上部の空間の長さを変えることで音高を変える」とか、「声帯の張力によって音高を変える」とか、いろいろな説が唱えられてきましたが、実際に音高を変える時の自分の発声器官の感触からは納得し得ないものでした。
| 声帯の音高コントロール機構 |
フレデリック・フースラー「うたうこと」より |
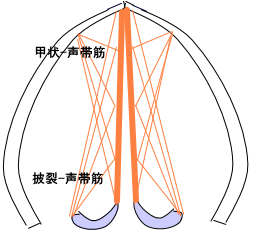 |
声帯の内部は、互いに交錯するいくつもの随意筋肉から成る複合体で、声唇と呼ばれる。
声唇を形成している交錯する筋は、各々別々に緊張したり弛緩したりでき、それによって声唇全体の形体を複雑に変化させることができる。
声唇は弾性の膜で覆われており、膜は声唇とは別の組織で、自力では動けず、声唇の表面をすべるように覆っている。
その膜のうち、縦に走る線維で形成される声門の縁は声帯靭帯と呼ばれ、この部分が主振動体になる。
交錯する筋の末端は声帯靭帯にまで達していて、それによって声帯靭帯はいくつかの同じ長さの部分に分割されている。交錯筋の末端はその自律運動によって、分割された部分を自由に限定して振動させることができる。バイオリンの弦を指で押さえて振動する長さを変えて音高をコントロールするようなしくみである。
|
|
1965年に出版された「うたうこと」の冒頭で、フースラーは『人類という種族には歌う能力がある。人間はそういうふうに作られている。ずっと昔には人間はだれでも歌ったものだ。・・・中略・・・おそらく、人間は原始時代に、きわめて長い期間、歌声に恵まれていた。しかしその声はまだ最も単純な音楽形式とも無関係だった。その歌声を持っていたのは、人間が話すことができるようになったときよりもずっと以前のことである。』と述べています。
フースラーによって解明されたことは、人類の発声器官が緻密な楽器になっていて、誰もがその構造と機能を等しく生まれ持っている・・・という客観的事実でした。
フースラーは更に、『・・・しかし、それ以来限りなく長い時が過ぎ去ってしまって、その間に人類は一般的にいろいろな程度の音声衰弱症にかかっている。それは発声の機構をずっと使わなかったせいである。』と後述してます。
「発声の機構をずっと使わなかったせい」というのは、やや大袈裟な表現ですが、言葉を話す時には発声器官の機能の一部しか使用されないことを指しています。
人類が言語社会を築き、言葉を発することが発声器官の主な仕事になると、使われる頻度が激減した発声器官の部分の諸筋肉は徐々に衰え、そういう発声器官が現代人に受け継がれている・・・という意味です。
生れ付き歌声の得意な人は、幸いに健康な発声器官に恵まれて生まれた人、と言い換えることができるのです。 |
 |
参考・引用文献
うたうこと フレデリック・フースラー 著
|
|
|