吟詠と音楽
いろいろな記譜法 五線譜は万能ではない 五線とト音記号 音名 音符と記号
| 五線とト音記号 | |||
| ト音記号はG記号の日本名です。 ト音はg音(ソ)のことで、第2線をト音(ソ)にするという約束の記号です。 高音部記号、ヴァイオリン記号とも言われます。 |
|||
| 五線と間 | |||
| 5本の線は、下から番号で呼びます。 線が足りなくなると、短い加線を書き、上(かみ)第○線、下(しも)第○線と呼びます。 |
|||
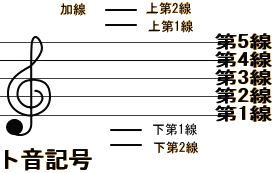 |
|||
| 線と線の間は間(かん)と呼びます。順番は線と同じです。 | |||
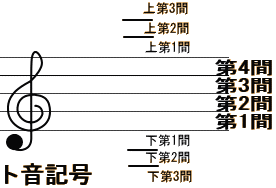 |
|||
| ト音記号譜の読み方 | |||
| 音高は線→間→線→間・・・と交互に上下進行します。 第2線から上へ「ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ」の並びになります。 何度も見ている内に、数えなくても読めるようになります。 |
|||
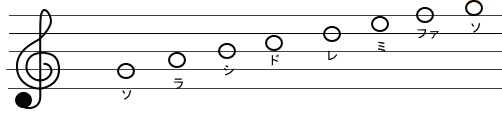 |
|||
| 下へは「ソ・ファ・ミ・レ・ド・シ・ラ・ソ」の並びになります。 | |||
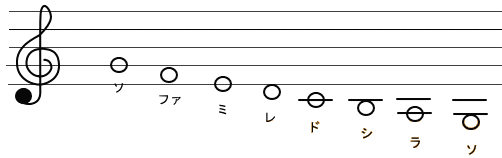 |
|||
| 全音程と半音程 | |||
| ふたつの音の高さの差を音程といいます。 1本と3本のような音程(2律差)を全音程と言います。 3本と4本のような音程(1律差)は全音程の半分という意味で半音程と言います |
|||
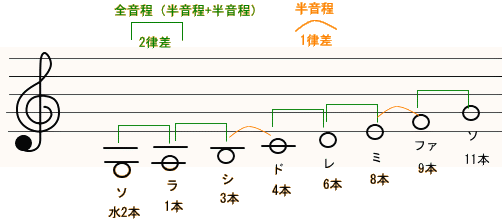 |
|||
| 上の譜面には2本がありません。 2本の音は、1本より半音程高く、3本より半音程低い、丁度真中の高さですから、臨時記号を付けて表します。 半音あげる時は♯(シャープ)、 下げる時は♭(フラット)を音符の前に付けます。 ♯ラと♭シは、同じ高さですから、どちらを使ってもいいのですが、便宜上一般的には2本は♭シで表します。 |
|||
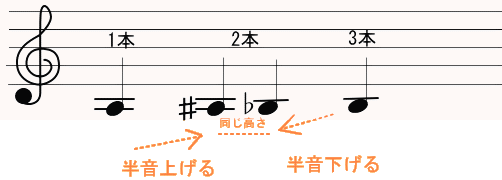 |
|||
| 同じ理屈で、7本は♭ミで表します。 5本は、♯ド、♭レのどちらでもいいと思います。 |
|||
| 全音程を音感で覚えよう | |||
| ■何か一つの高さを取ります。 ■その音から上へ全音程を歌ってみます。 たとえば「ソ・ラ・ソ」のように、ただし母音で歌います。 ■逆に下へ全音程の練習です。 たとえば「ソ・ファ・ソ」のように、ただし母音で歌います。 ■いろいろな高さから練習し、全音程の感じを覚えます。 |
|||
| 音程感をつける為の練習ですから、ボリュームたっぷりに歌う必要はありません。 むしろ、声を歯の先に当てる浅い発声の方が、音感が正しく養われます。 |
|||
| 半音程を音感で覚えよう | |||
| ■何かの音から上へ半音程歌う練習をします。 たとえば「ミ・ファ・ミ」、ただし母音で。 ■下へ半音程の練習です。 たとえば「ド・シ・ド」、ただし母音です。 ■いろいろな高さから練習し、半音程の感じを覚えます。 |
|||
| 全音程と半音程を交互に歌ってみる | |||
| 母音で歌います。 はじめは楽器に合わせて歌ってもいいでしょう。 正確に出来るようになると、声だけで行います。 ■「何かの高さから→上へ全音程→戻る」 ■「同じ高さから→上へ半音程→戻る」 ■「何かの高さから→下へ全音程→戻る」 ■「同じ高さから→下へ半音程→戻る」 |
|||
| 仲間がいる場合には、誰かが調子笛などで勝手な高さを鳴らしてもらい、その音から、全音程、半音程を歌うというゲーム的な練習も効果的です。 |
|||
| |